「十年一ヶ月と二十五日、私には師匠がいない」
二〇一七年七月十八日。
私が二代目玉川福太郎に弟子入りしたのが二〇〇七年三月五日。芸歴、十年四ヶ月と十三日。そのうち、十年一ヶ月と二十五日という期間、私には師匠がいない。
七月十八日というのは、この文章が配信された日であるから、翌日になれば、十年一ヶ月と二十六日、その翌日になれば二十七日。当たり前だが、一日経てば、私にとって師匠のいない日は一日増える。
私が師匠と過ごした二ヶ月十八日という日々は、もちろん増えることも減ることもない。

当たり前だが、若手のほとんどの人に師匠がいる。全員と言っていいのかもしれない。いや、いなければならないのが、この世界だ。ただ、“この世界”の中にも、少し差があって、特に浪曲界というのは、師匠がいないままに大看板(一流の浪曲師)になった先人たちが何人もいらっしゃる。誰々の門下、という肩書きではなく「独流」などとプロフィールに書かれていることを、一人や二人でなく見たことがある。落語・講談の世界で、これはない。二ツ目以下の芸人で師匠を亡くした場合は必ず、他の師匠の弟子にならなければならない。必ず。
浪曲界にその制度が適用されていたら、今日わたしは浪曲をやっていないと確信がある。誰の弟子でもいいから浪曲がやりたい、ということは全くなかった。
二ヶ月と十八日の間で、わたしなりにであるが、師匠福太郎に心底惚れ、「師弟というのは親子以上だからな」という言葉を、そのまま胸に刻み込んだ。いや、必死で真っ白な布になって、言われることすべてを素直に受け入れようと、無我夢中で刻み込んでいたような状況かもしれない。その最中、不慮の事故で目の前から消え去った。そのすぐ後に、「じゃあ、誰々師匠のところで弟子になれ」と言われて、受け入れられるわけがない。「親子以上の存在になる人」が、この世に二人も持てるはずがない。そういう人もいるが、わたしには無理だ。
おかみさん(みね子師匠)からも、他の師匠の預かりになっても良いと、具体的に名前を挙げて話をされたこともあったが、わたしは正直一秒も検討しなかった。強制的にそういうことになる状況があったら、前述の通り、わたしは辞めていたはずだ。
今、この文章を書きながら、ふと。
「わたしは浪曲への未練ではなく、師匠福太郎への未練で今日まで続けているのだろうか」ふとそんなことを思った。いや、そんなことはないと思うが、深層心理は自分でもわからない。
とにかく、わたしは浪曲師になって二ヶ月と十九日目から、ずっと師匠がいない。
「ソーゾーシー」というこの四人の中で、当たり前に並ばせてもらっているが、当然だが、お三方には師匠がいる。しかもピンピンしている。現役バリバリで活躍している。
はっきり言う。羨ましくてしょうがない。

師匠から仕事がもらえるとか、そういうことじゃない。(嘘をついた。当然それもある!当たり前だ!)一番尊敬し、一番憧れ、影響を存分に受けてよくて、受けたくて(まあ、受けたくなくてもいいけど)、芸を吸収できる対象が、この世にいるということ。こんなアドバンテージあるか、と思う。
たまに、「わたしは師匠からほとんど稽古をつけてもらったことがないんです」なんて言う人がいるが、それがどうした。何を偉そうに言ってやがる。稽古つけてもらえなくたって、生身で接することができて、会話することができて、いやそんなことより単純に、師匠の芸が存分に盗めるじゃないか。それ以上に何か望むことがあるのか。
福太郎の音源はある。映像もある。それこそ、擦り切れるくらい見聞きしているが、そう言うもんじゃない。舞台の、生の空気を通して触れる芸っていうのは、体への入り方がまるで違う。それこそ、テープ百回聴くのと舞台を袖から一回勉強するのじゃ、後者の方が血肉になると感じる。過去の固まった芸じゃなく、現在進行形で変わっていく「生きている芸」に自分が望めばいくらでも接することができる。羨ましくてしょうがない。
って、これ、二ツ目以下の芸人にとってはごく当たり前のことを、大げさに羨んでいるように聞こえたら勘弁してほしい。わたしには、その当たり前に「師匠がいる」と言う、本当に当たり前の、誰にとっても当たり前の感覚が、ない。
確かにいた。いた期間はある。どう言葉にしていいかわからないが、亡くなって一年目とか二年目とかの方が、今よりずっと喪失感が大きかったと思う。喪失感ではあっても、それはつまり師匠の存在感だ。しかし、三年四年五年六年、そして今年で十年と日が経つほど、喪失感すら麻痺してくる。いないことが、いなかったことが当然になる。師匠の弟子ではある。それはもう胸を張ってわたしは、福太郎の弟子だ。誇りだ。でもいない。ずーっといない。いない時間だけが積み重なっていく。
単純な劣等感、とも違う。申し訳なさと言おうか。なんか時折、すみません、と思う。インタビューとかで「やっぱり芸っていうのは、口伝で継承されるものなんですよね」って質問されたり、芸人仲間から「上げ(舞台にかけて良い、という許可)の稽古とかどうすんの?」と聞かれ、「いえ、音源とか台本を自分で覚えて、自分の判断で高座にかけます」と答える度、期待を裏切ってすみません、と思う。同じ土俵ですみません、と思う。
それで今日まで、浪曲師として続けてきた。十年四ヶ月と十三日。出来過ぎだなぁ、と思うこともある。
ソーゾーシーもそうだ。浪曲よりも圧倒的に競争の激しい業界において、頭角を現している皆さんと肩を並べさせてもらえる。こんな状況をいただける理由を考えると、その答えはわかりやすく一つだ。
「新作」をやる。やってきた。
だから、この場に立てている。多分去年くらいの高座数で言えば、浪曲師の中で一番多いんじゃないかと思う。(単価も日本一安いと思う)そんな状況を作れたのは、新作をやってきたから。明確に、そうだ。
新作をかける時、新作の会で競い合っている瞬間。前述したような申し訳なさからも、劣等感のようなものからも、知らず知らずのうちに、離れたわたしがいるのだと思う。そこにあるのはただ、お客さんが楽しんでくれたかどうか。失敗も成功も誰のせいでも手柄でもない。口伝も上げの稽古もありゃしない。わたしは浪曲師として間違いなく、新作をやることで救われた。新作をやることで得られた感覚や自信、それらが古典の演目にもどれほど影響しているかわからない。
師匠がいない日々は事実として日毎に積み重なる。
妬みや身の悲観、周りをうろつく負の感情どもから遠く離れるために、わたしにできることは、創作だ。創造だ。新作に限ったことではない。古典の世界でも独自の想像、創造がどれだけできるか。
わたしはわたし自身が浪曲師であり続けるために「創造し」続ける。
了
玉川太福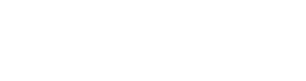

『ソーゾーシー』
- 春風亭昇々
- 瀧川鯉八
- 玉川太福
- 立川吉笑





